殺気を感じる女の子の日常と過去の事件。
いろいろな伏線が張られていて、一応それらすべてが線となって結ばれて完結する、
のでよいのだが、ハラハラドキドキ感はあまりなかったなあ。
波乱万丈なことが起こる女子大生ましろを描くのは楽しいだろうけど、
ストーリー自体はそれほどでもなかったと思います。
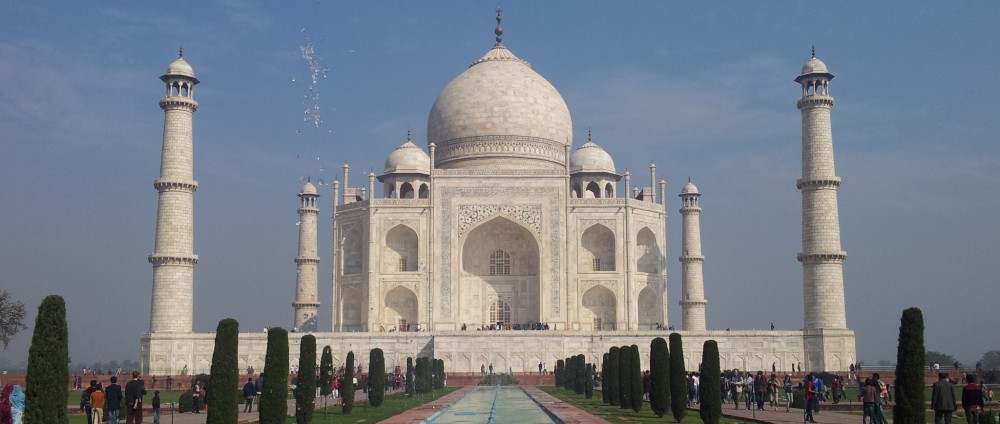
殺気を感じる女の子の日常と過去の事件。
いろいろな伏線が張られていて、一応それらすべてが線となって結ばれて完結する、
のでよいのだが、ハラハラドキドキ感はあまりなかったなあ。
波乱万丈なことが起こる女子大生ましろを描くのは楽しいだろうけど、
ストーリー自体はそれほどでもなかったと思います。
本屋でやたら平積みにされているので読んだ本。
無難に面白かったが、語り口調がちょっと読みづらいのはどうしたものか。
本文中で言い訳しているがそれ以上にちょっと読みづらいだけ、という印象が残る。
文体が表紙を担当したカスヤナガトのイラストとのギャップがちょっとありますけど、
このイラストに引かれて読んでも、読みやすい感じなのでよいとは思います。
というのも、医療ものっぽいタイトルの割りに、
そういうことをあまり感じさせない作品で、読みやすいとは思います。
どの辺が神様のカルテだったのかは分かりかねますが。
映画の「ゴールデンスランバー」を見てきました。
公開直後だったので混んでいるかとも思ったけど、
田舎の小さい劇場で、日曜の、レイトショーだったこともあって、ガラガラ。
大丈夫か?(汗
内容はかなり原作に忠実。
まあそれはともかく、伊坂作品らしく、うまく現在と過去を対比させながら進んでいく展開は秀逸。
中村監督が伊坂作品をよく理解しているとしかいえない。
最後の最後は、ああ、うまく戻ってきたなあ、という感じ。
ストーリーは、社会から逃げて逃げて逃げまくるという暗いテーマであるにもかかわらず、
作品自体に花マルのよくできましたをあげたくなりました。
12/26のブランチでも今年のお勧め作品に選ばれていたこの作品をちょうど読んでました。
そのときにも紹介されていたんだけど、どこかの国のあまり知られていない昔話を掘り起こしてきて、
そのまま伝えてくれているような、そんな不思議な感覚に包まれた。
口が塞がった状態で生まれてきた少年アリョーヒン。
ごくわずかな知り合い以外とは、チェスを通じて話をする。
チェスをすれば、その人がどんな人か分かる。口がふさがっていても何の不都合もなかったのだ。
そのことも含め、この作品には限られた空間、というキーワードがたくさん出てくる。
僕が解釈するとそれはそのままチェスのことを投影して、
限られた空間から生まれる美しさや、もうちょっと拡大解釈すればエネルギーのようなものを伝えたかったのかもしれない。
以下は数学好きだからこその曲解ですが、
前作「博士の愛した数式」というのは数学の美しさを誰もが感じられるような雰囲気であり、今作はそれをチェスに置き換えられる。
もちろんストーリーの展開は違うが、チェスの美しさを誰もが感じ取ることができる。
そもそも、チェスも数学も似ている。
どちらも、限られた世界での現象を考えるものという意味である。
その中で自由に羽ばたけるのは思考だけなのである。
数学やチェスといった無機質なものが、実は思考の先に有機的なものに変化する。
それがいかに美しいか、そのことを小川洋子という人はよく知る人、あるいはうまく伝える人なのだろう。
国分太一が主演の映画。落語家の不器用な生き方を描く。
だいぶ昔に原作を読んでいるんだけど、こないだテレビでやっていたのを録画して見た。
映画も小説版と同じく、ものすごく感動したりするところはないけど、
ほっこりするよい出来だったと思います。
重い、重すぎる!
前半に身につまされる内容が続いて、ひたすら暗い展開。本当に有川作品かと思うほどだった。
仕事もしない、親とも顔を合わさない、自分の思い通りにならないとヤダ、という、
フリーターというよりはただのダメ人間が、成長していくサクセスストーリー、とでもいうのだろうか。
前半は読んでいて重いですが、後半になるにつれて成長すると読みやすくなります。
読後感はそれほど悪いものでもないかと。
後半にならないと恋愛沙汰になるような女性が出てこないのも特徴的。
テーマは恋愛じゃないから、まあちょっと異色な作品と思っておけばよいと思います。でもよかったです。
作品途中に出てくる工事現場の無骨でも親切な人たちのような人ばっかりだったらいいのにねえ、と思いますが。
実は9連休に入っていました。
冬休みと繋がれば2週間ぐらいの休みになるところだったんですが、
仕事納めの28日だけ出社になってしまいました。
といっても、仕事の都合でこの時期になってしまっただけで、やることはほとんどないんですけどね。
夜はM-1グランプリ。
NON STYLEが敗者復活したところでは、今田さんに同じくちょっと鳥肌ものだった。
まあ、結果は納得かな。笑い飯はもうM-1を諦めているというか、ある意味楽しんでいるというか。
スリの生きる道。
最後がちょっと淡々としすぎていて期待はずれだたけど、全体的には面白かった。
確かにスリの話が感動のフィナーレを迎えても困るわけだし。
インテリ芸人宇治原さんのことを、相方である菅さんが書いた作品。
字が大きいので、読みきるのに1時間弱。なんだこりゃ。
書かれている内容は、高校生から芸人となるまでの間の二人の話。
とりあえずもともと賢い二人やから、なんで芸人の道を考えたのかということのほうが謎でしたし、
読んだあとでもやっぱり謎ですが。
宇治原さんの勉強の仕方は明確でよいと思います。
目的があって、それをやり遂げるために何をすべきか自己分析して、あとはそれを信じてやり通す。
当たり前のことをやったように書いていますが、それだけのことが凡人には難しいわけですけどね。
まあ、ロザンファンは一度読んでおけば? という程度の作品。
万華鏡とは言い得て妙。
同じものをいろいろな角度から見るということが、
京都が持つ不思議な空気を際立てる。
っていうか、京都は別に不思議な空気を持っているわけじゃないんだけど、
森見先生の手に掛かると不思議な街に見えてしまうからしょうがない。